育休復帰前に、どんな知識や技術を確認しておけば仕事で困らないだろうか……?
そんな不安や疑問を抱える、育休復帰前の看護師さんも多いと思います。
わたしも復帰前に勉強方法について調べていましたが、ネット上には「基礎看護技術」「自分の診療科にまつわる知識や技術」「検査データや薬について」などふわっとしたことしか書いてなくて、途方にくれました。
最終的には自分で取捨選択して決めるにしても「指標として確認すべき項目リストぐらいは欲しい……!」と、その時に思ったのです。きっと同じような思いを抱える育休中のママさんも多いはずです。
そこで今回は看護師歴11年目の私が、看護書籍20冊以上を参考に
「復帰前に確認しておくと良い具体的な看護知識や技術のチェックリスト」を作りました。

- どの順番でどの点に着目しながら学び直せば、頭に入ってきやすいのか?
- 優先順位の高いものはどれか?
- 体系的に抜けなく学ぶために、チェックリストをどうまとめるか?
以上の点に気をつけつつ、実際に育休復帰前に自分の勉強しながらまとめました!
これはあくまで指標です。所属部署や経験によっては不要な項目もありますが、一度目をとおしてみてください。チェックボックス部分をスマホでスクショしておけば、抜けがないか確認できるのでおすすめです。
量がかなりあるので「多いなぁ……」とげんなりしてしまう人は、太字のものだけでもチェックしてみると良いと思います。効率よくできるよう各項目ごとにポイントも紹介しているので、よければ参考にしてみてください。
復帰して仕事をするうちに、あのとき調べておいて良かった!と思える瞬間がきっとあるはずです。

看護技術
- 遭遇頻度
- 患者への侵襲性
- 緊急性が高いもの
以上を優先的に列挙しています。(たとえばシーツ交換などは侵襲性や緊急性が低いのではぶいています)
上から順番に、自信のないものや所属部署に必要そうなものから復習してみてください。

- 感染対策……個人防護具の着脱順序
- 採血
- 静脈路確保
- 点滴滴下に関する手技……自然滴下計算方法、点滴が落ちない時の対処法
- 皮下注射、筋肉注射
- 輸液ポンプ、シリンジポンプ……使用方法、アラーム対応
- おむつ交換、陰部洗浄
- 浣腸
- 摘便
- 体位変換
- 移乗介助
- 食事介助
- 清潔ケア……口腔ケア、ベッド上洗髪
- 胃ろう栄養……管理、投与方法
- 経管チューブ挿入介助……経管栄養の管理、投与方法も
- 吸引……鼻腔/口腔/気管内の吸引手技、体位ドレナージ等の排痰テクニック
- 血糖測定
- インスリン製剤投与方法
- 血液培養検査の採取方法
- 尿道カテーテル留置
- 12誘動心電図
- 輸血……各種血液製剤の特徴、管理方法の違い、副作用
- CV/PICC刺入部のガーゼ交換
- 酸素療法……酸素投与器具の種類と特徴
看護手技に関してはコレ!という正解手順がありません。
病院や病棟によっては使用物品や手技の順番など細かいところが違うと思います。
あらかじめ書籍やネット検索などで技術を復習し直しておいて、復帰後早めに病院や病棟のマニュアルを確認しておくと安心です。
看護知識
次は看護知識についてです。
- 遭遇頻度
- 緊急性
- 重症化リスク
以上の点が高いものを中心に挙げました。
上記の看護技術とかぶる部分は省いています。
一般的な知識
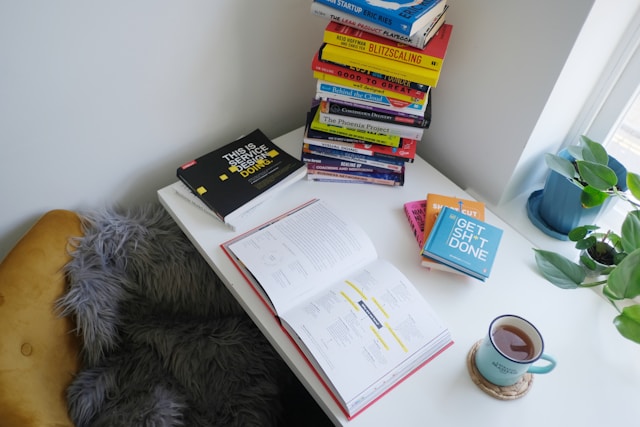
- 感染症対策……ゾーン分け、標準予防策
- バイタルサイン……異常値、原因(考えられる病態)、対応
- 発熱、解熱のプロセス
- 呼吸音……聴診時のポイント、4種類の副雑音、考えられる病態
- 意識障害……考えられる病態、対応
- 血糖値……基準値、低血糖高血糖時の対応、薬剤投与後の評価方法
- 尿量……基準値、原因3つ(腎前性、腎性、腎後性)、尿蛋白尿糖陽性の意味
- 輸液①……目的4つ(★循環血液量の維持、水電解質バランス補正、栄養補給、原疾患治療)、★最優先
- 輸液②……1号〜4号輸液、効能の違いや使い分け方(細胞外液補充液、維持輸液)※現場でよく使う薬剤名で覚える
- 簡易モニター心電図(波形の読み方、アラーム対応)
- 経腸栄養(栄養剤の種類や効能)
- 包帯法
- ドレーンの管理(目的、種類、特徴、扱い方)
- 創傷管理
ちなみに経腸栄養剤のエレンタール/ラコール/エンシュアなどは医薬品扱い(医師の処方)になるので、その辺の周辺知識も知っておくと便利です。
高齢者に特に関係する知識

- 褥瘡管理(好発部位、リスクアセスメントスケール、洗浄手順、ドレッシング材の種類と違い、外用薬の効能の違い)
- 体圧分散マットレス(病院にあるマットレスの違い)
- 日常生活自立度(J1〜C2まで)
- 脳卒中(脳梗塞/脳出血/くも膜下出血)の原因と症状、治療、麻痺の評価
- 人工呼吸器管理(モード/アラームの種類)
今回のリスト化にあたり疾病の分野は際限がないため入れていないのですが、脳卒中に関する知識は覚え直しておいて損はないのでリストに入れました。なぜなら、遭遇頻度・緊急性・重症化リスクのどれをとっても高いからです。
人工呼吸器管理に関しては、メーカーごとに設定の名前が全く違います。
職場で使っている機種を確認してからアラームの種類やモードの違いを復習し直す方が効率が良いので、すぐ使うような部署でなければ復帰後でも大丈夫です。
病院的に可能であれば、呼吸器のモニター画面をスマホで撮って勉強し直すとわかりやすく効率的です。
急変対応に関する知識

遭遇頻度は低いですが、緊急性と重症化リスクが高い分野です。
- 意識障害の原因
- 急変の前触れのよくあるサイン、いくつか例を見ておく
- バイタルサインの関連図把握……循環(BP、P、皮膚、尿量)、呼吸(回数と深さ、SPO2)、意識(意識レベル、血糖、反射)
- 一次救命(BLS)
- ABCDEサイクル
- ショック……ショックの5徴、種類(循環血液量減少性、敗血症、アナフィラキシー)
- JCS/GCS
- アナフィラキシーショック……全身症状、対応、治療方法
- 緊急薬剤の種類と効能、使い方、別名、緊急カートのどこになんの薬剤が入っているか
- 心停止の4つの病態(VF、VT、PEA、Asystole)とその初期対応の違い
- 気管内挿管の介助方法
- CV挿入介助(マキシマル・バリア・プリコーション)
なかでも特に重要なものについて補足説明します。
意識障害の原因
急変対応の始まりのひとつです。
意識障害の原因はなにか?何を確認しどう対応するか?自分で思いつくだけ紙やメモアプリに書いてみましょう。頭に思い浮かべるだけでも大丈夫です。その後、自分でも思い至らなかったものはないか、調べてみましょう。
もし余裕がある人は、(バイタルサインの関連図の把握、BLS、ABCDEサイクル、ショックの5徴)を復習し直したあとに、急変初期の対応方法を自分なりに考えておきましょう。
個人的には、迷ったら「呼びかけながら頸動脈で脈を確認、ABCDEサイクルに従って異常がないか確認」と決めています。呼びかけに応える=意識・気道(Earway)OK、脈拍測定で大体の血圧値と脈拍数確認、その後に残りのABCDE確認事項などをチェック、対応(人を呼ぶ、救急カート、Dr報告、ルート確保・心電図装着など)といった感じです。もちろん状況や環境で順番が前後しますし、私自身の思い出しやすさから決めているので、この限りではありません。
緊急薬剤の別名
Drに別名で呼ばれる事があるためです。
実際私の職場でも、アドレナリンのことを「ボスミン1A静注!」と言われるも2年目の子が見つけられず焦っていたことがありました。緊急薬剤使用時はどんなベテランでも緊張しますし、普段使わない薬剤の別名なら尚更、とっさに脳内変換出来なくても不思議ではありません。だからこそ確認しておきましょう。
緊急薬剤
復帰後なるべく早く救急カートの中身を把握しておくことが重要です。
人工呼吸器管理のところで述べたように、職場的に写真撮影可であれば一段ずつカート内を撮っておくと勉強がやりやすいです(薬剤のラベルを上に向けて撮るとよりGOOD)。
難しければ、カート内に入っている薬剤名を1つずつメモしておく手もあります。
時間に余裕があるときに調べておくことで、いざというときの安心に繋がります。
心停止の4つの病態とその初期対応の違い
簡単に書くと「VT、VFはBLSに沿って進めつつ除細動準備」「PEAとAsystoleは早急にアドレナリン投与の必要性あり=ルート確保」です。
心停止の場面にはそうそう出くわしませんが、初動時に対応を思い浮かべていることが肝心です。万が一に備えてどう動けば良いのか、最初の一歩が踏み出せるように知識を確認しておけるといいです。
気管内挿管の介助
かなりの緊急事態です。いざ挿管!となった場合、もたついていると患者の命に関わります。ただ経験する機会も練習する機会も滅多にありませんので、定期的にYouTubeなどで動画を見返しておくと安心です。
薬関係の知識

- 与薬原則の5R(6R)
- 内服薬
- 貼付薬
- 点眼薬
- 点耳薬
- 点鼻薬
- 座薬
- 点滴薬(メイン点滴/ビタミン剤/高カロリー輸液など、よく使用しているもの)
- インスリン製剤(持続型・超速効型・中間型など)
- 吸入器(MDI、DPIなどの携帯可能なもの)
「経皮投与」などの投与経路別にまとめず、あえて臨床現場でよく使う言葉で列挙しました。
自分の過去のメモ帳や勉強ノートがあれば確認しましょう。ネットの画像検索で「看護 薬」と入れ、出てきた検索結果をぼーっと眺めるのでもいいですね。気になるものや、これはあまり覚えていないな……と思ったものをピックアップして深堀りしていくのも興味に沿った勉強になるのでおすすめです。
現場でよく遭遇する内服薬
- 降圧薬
- 血糖降下薬
- 便秘薬
- 解熱鎮痛剤
- 睡眠薬/不穏時の薬
- 麻薬(オピオイド鎮痛薬)の薬剤名、商品名、効能や副作用、管理方法
上記の薬は元々服用している患者が多いです。
病棟勤めだと、熱発時や疼痛時、不眠・不穏時の指示薬として使用することもあるはずです。
それぞれの薬で確認すること
- 効能
- 副作用
- 管理方法
- 投与経路と投与方法
- 投与の順番(点眼薬など)
頻度は低いですが、舌下錠や眼軟膏の投与方法も一度目を通しておくといざというときに役立ちます。
調べ直しておくと臨床現場ですぐ役立つこと
- 血液サラサラ系の薬(抗血小板薬と抗凝固薬)
- 薬と飲み合わせの悪い食物(納豆/グレープフルーツなど)
- 点滴の代替薬がどの内服薬になるのか
- GI療法(グルコース・インスリン療法)
個人的にしっかり覚え直しておくと仕事で有利だったのは、血液サラサラ系の抗血小板薬と抗凝固薬についてです。抗血小板薬は動脈(動脈硬化を伴う血栓)、抗凝固薬は静脈(血流の停滞で起こる血栓)に対して使用している、というのがポイントです。
↑こちらの本に詳しく書いてあったのでとても勉強になりました。
GI療法は高カリウム血症に対する治療です。どの病棟でもよく行われていますが、知らずに投与している人もいるかもしれません。ネット検索でもすぐ出てくるので、ピンと来ない人はサクッと調べてしまいましょう。(他にもメイロン投与やケイキサレート、カリメートの投与などの治療法もあります)
内服薬に関しては優先度が低めでも良いかもしれません。量が膨大なのと、いざわからないというときはその場で調べられるからです。
新薬も次々出てきますし、病院で契約して使っている使用薬剤や患者の持ち込み薬によっても違ってきます。内服薬はさらっと目を通す程度にして、復帰後に調べながら覚えるということにするのも1つの手です。
検査値関係の知識

- 臨床でよく使う検査値の略語と基準値(ふわっと)
- 病態と検査値の関連(感染症でCRPとWBCが上がる、貧血でHbが下がるなど)
- 自覚症状や身体所見
検査基準値は病院ごとに違いますし、電子カルテだと検査データの横に基準値も一緒に書いてあることが多いので完璧に記憶する必要はありません。ふわっと、「あーTPは6.5〜8.0くらいだな」などと自分のなかでキリの良い数字に変換し直して覚えなおす程度で十分です。
検査値は生化学や免疫血清などのジャンル毎に分類しているものが多いですが、「肝臓に関する検査値」など、臓器別にまとめてあるものがあれば覚えやすく復習しやすいです。インスタで「検査値」と検索するとわかりやすいものが出てくるので、参考にしてみてください。ただ個人の方が描かれている物が多く信憑性については保証出来ないので、病院のデータや書籍などで二重確認すると安心です。
この書籍は、病態からこういう検査値の異常が出るのはなぜか?という点に焦点をあてて解説しています。
文章が多めですが読み応えがあるので、じっくりと勉強したい人にはおすすめです。
- 医師カルテから検査値の異常値を確認して、現在の病態や治療の意味を理解できるようになった!
- 血液データから検査値の異常値を発見、アセスメントをして、病態の理解に繋げられた!
こんなふうに検査データを読み解いて使いこなせるようになれると嬉しいですね。
覚え直した知識、新しく知った知識は現場ですぐ使える

10年以上看護の仕事をしていて思うのが、看護の現場では学んだ知識を仕事で生かせる場面がすぐに来るということです。
「このあいだ仕入れた知識のおかげで、今日の患者さんの治療について理解が進んだ」
「患者さんに知識を還元して、痛みや不安を和らげる手伝いが出来た」
そう感じることが本当に多いのです。
知識が実践で使えると嬉しいですし、感謝されればやりがいにも繋がります。
仕事がスムーズに進んで時間短縮にも繋がれば、定時退勤に近づくという我々のメリットにもなります。
やるべき勉強量が多いとつい億劫になりがちですが、この知識・技術チェックリストがみなさまの復習・勉強の助けになれば幸いです。




